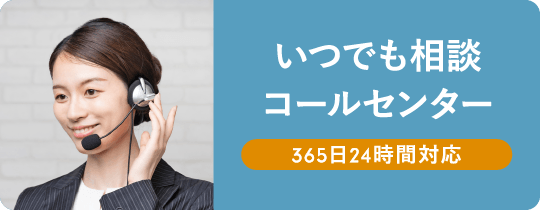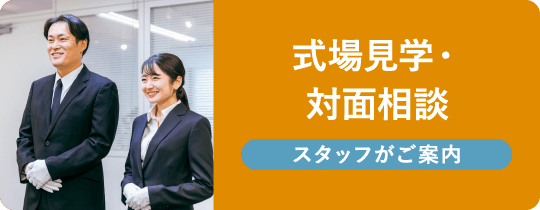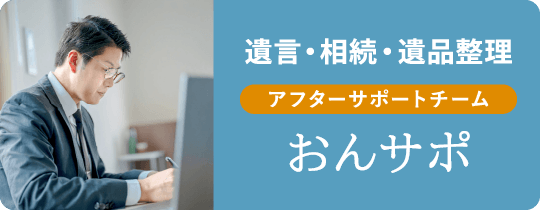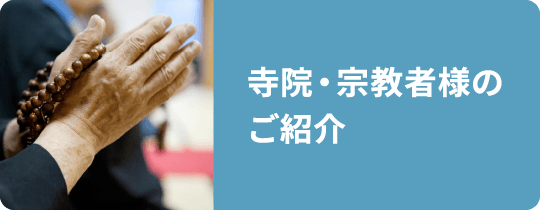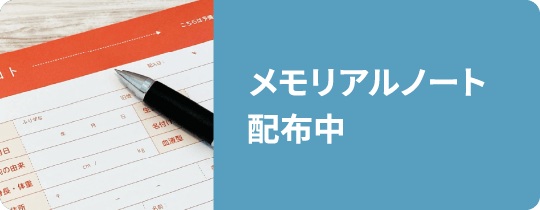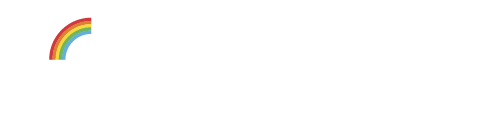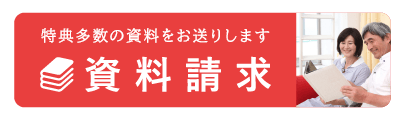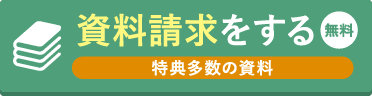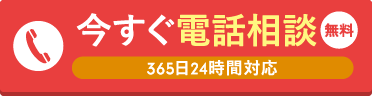「お盆」と「お彼岸」

お盆とお彼岸の違いとは?由来や意味を解説
もうすぐ8月のお盆がやってきます。お盆は先祖供養の行事として広く知られていますが、「お彼岸」と混同されることも多いようです。お盆とお彼岸は、どちらもご先祖様を供養するという点では共通していますが、由来や意味は異なります。
お彼岸とは?
お彼岸は、春分の日(3月)と秋分の日(9月)を中心とした前後3日間を含めた7日間を指します。お彼岸の由来は、仏教の考え方に基づいています。
私たちが住むこの現世は「此岸(しがん)」と呼ばれ、煩悩に満ちた世界とされています。一方、彼岸は「悟りの世界」を指し、六波羅蜜(ろっぱらみつ)と呼ばれる6つの修行(布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧)を行うことで、此岸から彼岸へ行けるとされています。
なぜ春分・秋分の日に行うのか?
春分と秋分は、太陽が真東から昇り、真西に沈む特別な日です。仏教の教えでは、十億万仏土先の西方に阿弥陀如来がいるとされており、春分と秋分は彼岸と此岸が最も近くなる日だと考えられていました。そのため、この時期に修行を行うことで彼岸へ行けると信じられていました。
お彼岸とお盆の違い
お彼岸とお盆の大きな違いは、先祖の霊との関わり方にあります。
- お盆:先祖の霊があの世から私たちの元へ帰ってくる
- お彼岸:私たちが先祖のいる彼岸へと近づいていく
お盆では、家の中で迎え火を焚き、ご先祖様をお迎えする風習がありますが、お彼岸では、私たちがご先祖様のもとに足を運び、お墓参りや供養を行います。
お彼岸は日本独自の風習
「彼岸」という言葉自体は仏教用語ですが、お彼岸の風習は日本独自の文化です。中国やインドには同様の行事はありません。日本では、春は種をまき、秋は収穫を迎える大切な時期です。五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈る風習がもともと存在しており、これが仏教の彼岸の考え方と結びついたのではないかと考えられています。
お彼岸とお盆の共通点
お盆もお彼岸も、共通するのは「ご先祖様を供養する」ということです。時期や由来は異なりますが、どちらも大切なご先祖様を想い、感謝の気持ちを伝える機会です。
セレモニーサポート・オンリーワンでは、お彼岸のご供養に関するご相談やご不安ごとにも対応しております。お墓参りの準備や供養の進め方など、些細なことでもお気軽にご相談ください。