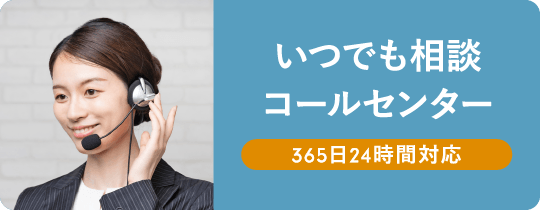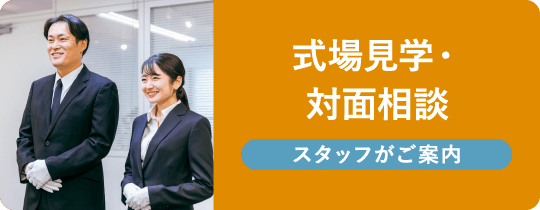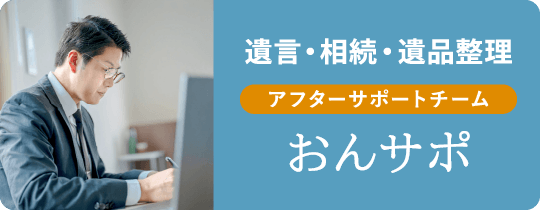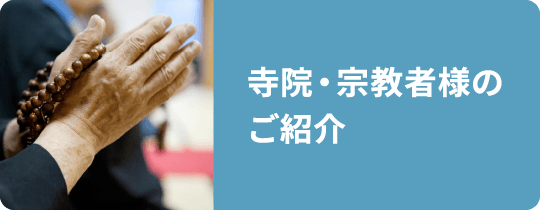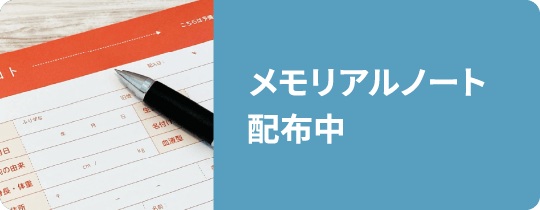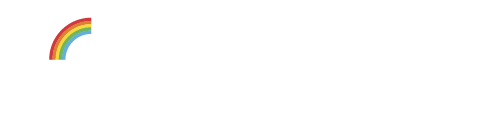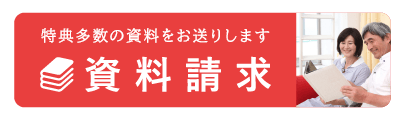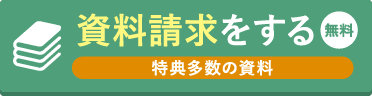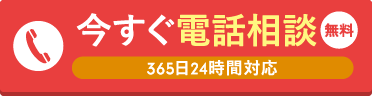成年後見人

「成年後見制度」についての基礎知識
近年、成年後見制度についてのご質問をいただく機会が増えています。今回は、成年後見制度の基本的な内容をお伝えします。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分な人を保護するための制度です。高齢や障がいなどにより、財産の管理や契約が自分では難しい場合、後見人が代わりに手続きを行い、本人の財産と権利を守ることを目的としています。
この制度は、平成12年に介護保険制度とともにスタートしました。
後見人とは誰がなれるのか?
法律では、後見人になれない人(欠格事由)が定められていますが、それ以外であれば誰でも後見人になることが可能です。
- 親族(家族や親族が後見人になるケースが多い)
- 専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)
- 市民後見人(地域のボランティア市民が後見人を担うケースも増えています)
- 法人後見(NPO法人や社会福祉法人が後見人となるケースもあります)
後見人を決めるのは家庭裁判所
後見人は、家庭裁判所が選任します。親族が後見人候補者として申請しても、必ずしも希望通りの後見人が選ばれるわけではありません。
- 親族間に意見の対立がある場合
- 不動産売買や保険金受領など、大きな法律行為が絡む場合
このような場合は、専門家(弁護士や司法書士)が選ばれることもあります。不服があっても、家庭裁判所の決定に異議を申し立てることはできません。
後見人が専門家になるケース
特に財産が多い場合は、弁護士や司法書士が後見人になるケースが多いです。理由は、「後見制度支援信託」が関わるからです。
後見制度支援信託とは?
「後見制度支援信託」とは、後見人がすべての財産を管理するのではなく、日常の支払いに必要な金銭は後見人が管理し、それ以外の金銭は信託銀行に信託する仕組みです。信託銀行と専門的な契約が必要になるため、弁護士や司法書士が後見人として選ばれるケースが増えます。
- 対象の財産目安:流動資産が500万円以上の場合
- 目的:本人の財産が不正に使われるのを防ぐ
死後事務委任契約とは?
後見人が担う業務の一つに、「死後事務委任契約」があります。
【後見人が行う死後の手続き】
- 特定の財産の保存に必要な行為(例:亡くなった後の部屋の片付けや不動産の管理)
- 相続財産に属する債務の弁済(支払期限が過ぎているものの支払い)
- 火葬や埋葬に関する手続き(火葬許可証の取得や、火葬・埋葬に関する契約手続き)
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがある
①法定後見制度 すでに判断能力が低下している場合
家庭裁判所が後見人を選び、本人の代わりに財産管理や契約の手続きを行う制度。
②任意後見制度 将来に備えてあらかじめ準備
本人が元気なうちに後見人を選び、任意後見契約を公正証書で結ぶ制度。判断能力が低下した際に契約が発動する。
法定後見制度とは?
すでに判断能力が不十分な場合、家庭裁判所が後見人を選任し、本人に代わって財産や権利を守る仕組みです。
任意後見制度とは?
将来に備えるための制度です。判断能力が低下する前に、本人が自ら信頼できる人を後見人に選び、契約を交わしておくのが特徴です。
この契約は公正証書で行い、判断能力が低下した際に契約が発動する仕組みになっています。
セレモニーサポート・オンリーワンの取り組み
セレモニーサポート・オンリーワンでは、成年後見制度に関する相談も受け付けています。大切な家族のことだからこそ、後見制度の仕組みを事前に理解し、相談しておくことが重要です。気になることがございましたらぜひお気軽にご相談ください。