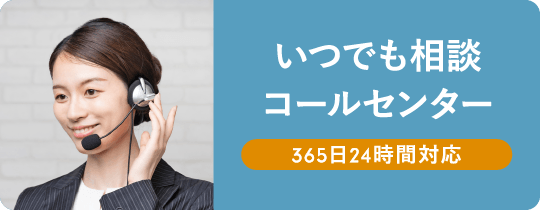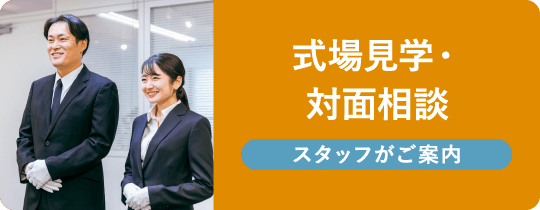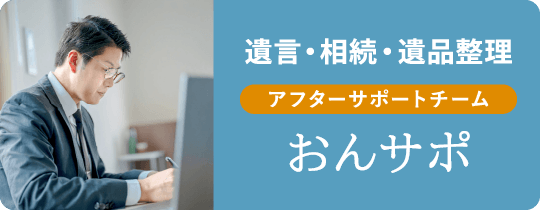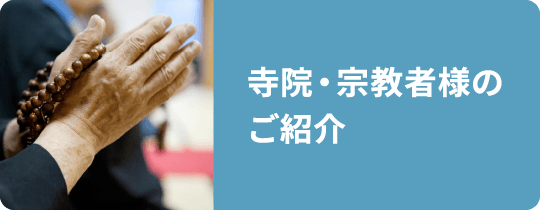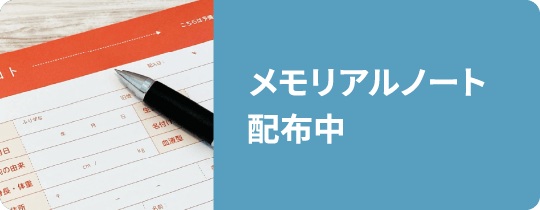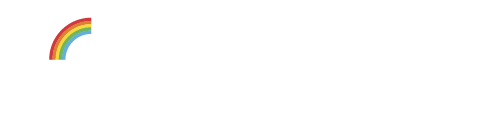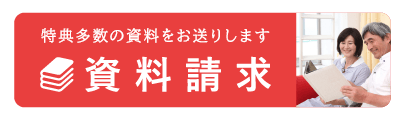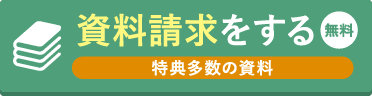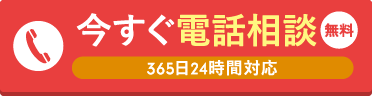成年後見制度 後編

法定後見の3つの類型「後見・保佐・補助」について
今回は、前回に続き、「後見・保佐・補助」の詳細をお伝えします。これらは、本人の判断能力の程度によって支援の内容が異なる制度で、成年後見制度の一環として位置づけられています。
■ 後見の対象となる方
対象者: 日常の買い物が全くできないなど、判断能力がほぼない方
後見人の役割
- 財産管理や法律行為の代理
- 取消権の行使(被後見人が行った法律行為を取り消す権限)
例えば、不動産の売却や自宅の処分を行う際には、家庭裁判所の許可が必要です。後見人は被後見人の生活全般を支える強力なサポート役です。
■ 保佐の対象となる方
対象者: 日常の買い物はできるが、重要な財産行為を一人で行うのは不安な方
保佐人の役割
- 重要な財産に関する行為の同意権(借金や不動産の売買、相続の放棄、訴訟の手続きなど)
- 取消権の行使(同意を得ずに行った行為を取り消す権限)
保佐は、必要な支援のみを受けられる柔軟な制度です。家庭裁判所の審判によって、保佐人が特定の代理権を持つことも可能です。
■ 補助の対象となる方
対象者: 日常の買い物は問題なくできるが、一部の重要な財産行為については援助が必要な方
補助人の役割
- 同意権と取消権の付与(家庭裁判所の審判により、被補助人が行う財産行為の一部に同意が必要になる)
- 代理権の追加(家庭裁判所の審判を通して、補助人に特定の法律行為の代理権が付与される)
補助は最も軽い支援制度で、支援が必要な一部の行為だけに関与します。例えば、新築の家の建設や不動産の管理がこれに該当するケースが多いです。
■ 後見人の主な仕事
- 預貯金の管理・解約
- 介護保険の契約(施設入所などの支援)
- 身上監護(健康管理、生活支援など)
- 不動産の処分(売却や賃貸契約の締結)
- 相続手続(相続財産の管理や分配の手続き)
- 死後事務の手続き(葬儀手配や死亡届の提出)
これらの業務は、日常の生活サポートから財産管理や法律行為の代行まで多岐にわたります。依頼する仕事内容に応じて、費用が変動するため、事前の見積もりが大切です。
お気軽にご相談ください!
成年後見制度は、状況に応じて最適な支援の形を選択する必要があります。「後見」「保佐」「補助」のいずれが適しているか、**オンリーワンの「おんさぽ事業部」**が親身になってご相談をお受けいたします。
些細な疑問や不安でも、まずはお気軽にご連絡ください。