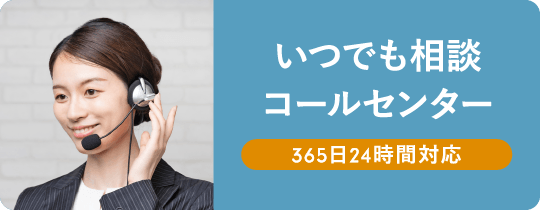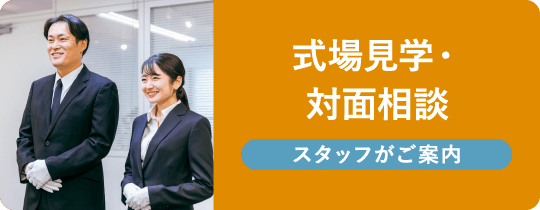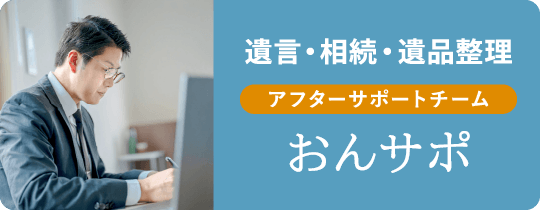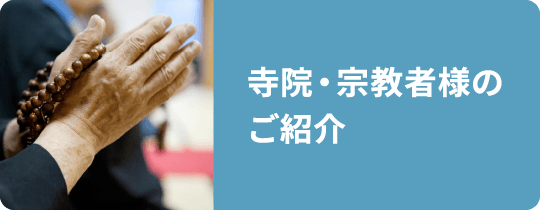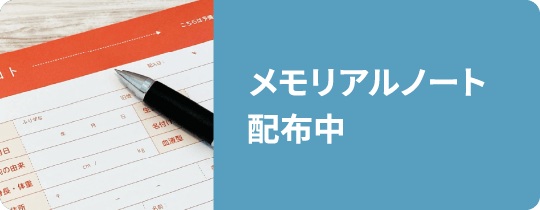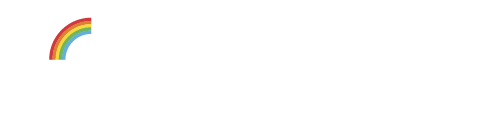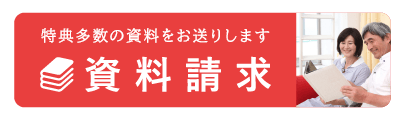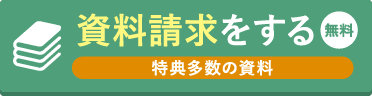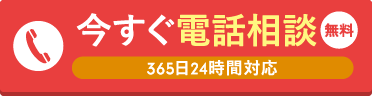お施餓鬼

雨が続く梅雨の季節、そしてお盆が近づいて
連日の雨で革靴が濡れてしまい、早く梅雨が明けないかと願う日々です。年々春を感じる間もなく夏が訪れるような気がします。
普段の生活の中で、なんとなく知っている言葉やイメージはあっても、その本質や真の意味を理解できていないことが多いと感じることがあります。今回のテーマである**「お施餓鬼」**についても、耳にしたことがあるものの、具体的な意味を知らない方が多いのではないでしょうか。そこで今回は、お施餓鬼の意味についてお話しします。
「餓鬼」とは何か
「餓鬼」と聞くと、何となくネガティブなイメージを持たれるかもしれませんが、これは生前の悪行や俗世で供養されず無縁仏となった霊や魂のことを指します。餓鬼たちは常に飢えと渇きに苦しむ存在とされ、その世界は「餓鬼道」と呼ばれます。この餓鬼道は、仏教でいう六道の一つで、輪廻の中で非常に苦しい世界の一つとされています。
「お施餓鬼」の本質
「お施餓鬼」とは、餓鬼たちに食べ物などの供物を施す行為を指します。この行為は、餓鬼たちの苦しみを和らげるだけでなく、この世にいる私たち自身の極楽往生や追善供養を願うものでもあります。
お施餓鬼は特定の月日に限定されているわけではありませんが、一般的にはお盆の時期に行われることが多い行事です。また、仏教において非常に重要な意味を持つため、多くの寺院が力を入れて行っています。
日常に息づく仏教行事
お施餓鬼は、普段の生活では意識しづらいかもしれませんが、実は私たちの暮らしにも深く関わっている仏教行事の一つです。もし興味があれば、近くのお寺で行われているお施餓鬼の様子を見に行ってみてはいかがでしょうか?
仏教は意外にも身近なものです。新たな発見を通じて、私たちの生活により深い意味を見出す機会になるかもしれません。