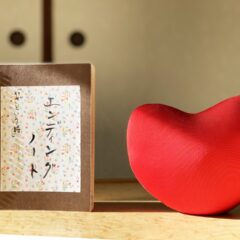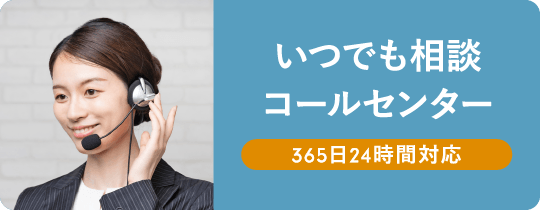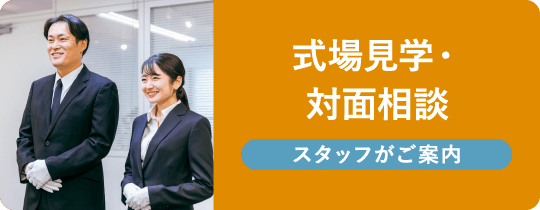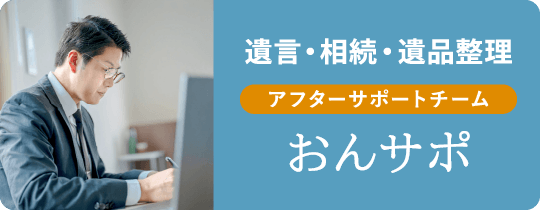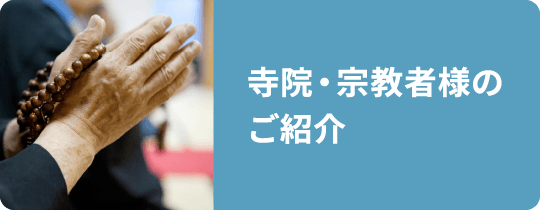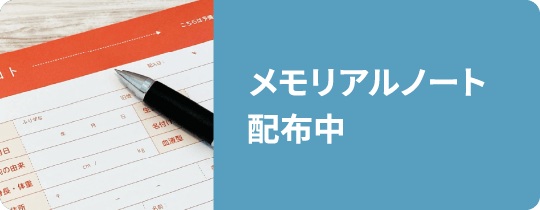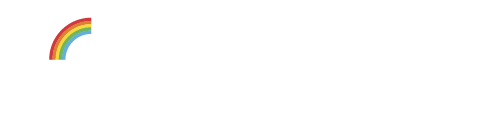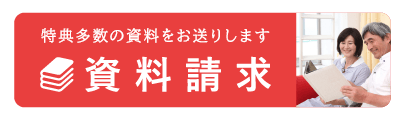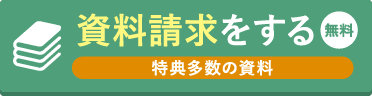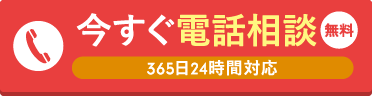御用納め
2025/12/29
官公庁では「御用納め」、民間企業では「仕事納め」と言いますが、葬儀社には特にこれといった区切りがありません。 私たち葬儀社は、年中無休で24時間体制。同じようにサービス業の方々も、この時期忙しくお仕事をされていることでしょう。 お葬式の文化では、「新年に不幸を持ち越さない」という考え方が昔からあります。 そのため、御香典返しを葬儀当日に済ませたり、葬儀代金を年内中にお支払いしたりと、さまざまな慣習 […]
年末の大掃除
2025/12/27
年の瀬が近づき、あちこちで大掃除に励む様子が見られるこの季節。 私も妻に尻を叩かれ、休日の予定に「片付け」や「すす払い」が強制的に組み込まれました。これも師走ならではの行事、と自分に言い聞かせながら動き出したところです。 掃除をしていると、不意に「断捨離」という言葉が浮かびました。 “物に執着せず、身の回りを軽くすること” という考え方だそうです。年齢を重ねた今、私もいよいよ考える時が来たのかと感 […]
年末年始
2025/12/25
早いもので、あと1週間ほどで今年も終わりを迎えますね。 年末年始は何かと慌ただしい時期ですが、私たちセレモニーサポート・オンリーワン協同組合は、24時間365日体制でお客様をサポートしています。年末年始も休まず営業しておりますので、いつでもご相談いただけます。 鶴見葬斎館、中央葬斎館、横浜かなざわ葬斎館、とつか葬斎館の各会館も、通常どおり開館しております。急なご相談やお問い合わせがございましたら、 […]
喪中の年末年始の過ごし方
2025/12/23
喪中の方の年末年始の過ごし方について 早いもので、今年も残りわずかとなりました。年末年始を迎えるにあたり、喪中の方はどのように過ごせばよいか、気になる方も多いかと思います。今回は、喪中の方の年末年始の過ごし方についてご紹介します。 【年末の過ごし方】 ✅ 大掃除 → しても良い大掃除はお祝いごとではないため、問題ありません。気持ちよく新年を迎えるためにも、普段通り行いましょう。 ✅ お歳暮を贈る […]
いつでもお問い合わせください
2025/12/21
今年も残すところわずかとなりました。 その中で、今年も人形供養祭を無事に開催することができました。おかげさまで、1200体以上のお人形を供養することができ、多くの方々にご参加いただきました。 ご参加いただいた皆さまには、アンケートへのご協力もお願いしました。その中でいただいたお声の一つに、 「問い合わせ時、丁寧な対応をしてくださり、葬儀の時でも家族が安心できるのではと感じました。」 という嬉しいご […]
冬支度
2025/12/19
セレモニーサポートオンリーワン協同組合のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。早いもので2025年も残りわずかとなりましたね。 私たちは、クリスマスや年末年始を問わず、365日24時間体制で対応しております。この冬の季節、葬儀業界では「繁忙期」と呼ばれることがあります。他の季節に比べてお亡くなりになる方が増える傾向があると感じるのは、寒さによる体調悪化や突然の事故、病気など、さま […]
北枕
2025/12/17
寒さが身に染みる季節となり、今年も残りわずかとなりましたね。皆様にとって、この一年はどのような年だったでしょうか? 今日は「北枕」についてお話ししたいと思います。 北枕とは? 北枕とは、頭を北に向けて寝ることを指します。この習慣の起源は、お釈迦様が入滅(亡くなられた)された際の姿勢に由来しています。正確には、頭を北、顔を西に向け、右脇を下にして横たわる姿勢のことで、「頭北面西右脇臥(ずほくめんさい […]
冬の火葬場…
2025/12/15
冬の寒さが厳しい12月から翌年2月にかけては、亡くなる方が増えやすい季節です。そのため、火葬場の予約を取るのが特に難しくなります。年末年始ともなれば、その状況はさらに厳しさを増します。 セレモニーサポート・オンリーワン協同組合では、川崎、横浜、横須賀エリアを中心にご葬儀をお手伝いしておりますが、特に横浜エリアでは火葬場の予約が1週間待ちになることも珍しくありません。それが年末年始となると、多くの火 […]
喪中はがき。書き方やマナー
2025/12/13
喪中はがきを出す時期になると、どこか心が引き締まるような気持ちになりますね。喪中はがきは、「年始のあいさつを控えさせていただきます」というお知らせですが、それだけではなく、故人の逝去を知らせる大切な手段でもあります。 近年は家族葬など小規模な葬儀が増え、身近な人以外には訃報が届かないケースも多くなっています。そんな中、喪中はがきを受け取ることで初めて、故人のことを知るという方も少なくありません。お […]
「アッ!という間」
2025/12/11
あっという間に過ぎる一年、時間の感じ方と終活のすすめ 今年も残すところわずかとなりました。毎年、「あっという間だった」と感じる方も多いのではないでしょうか? 実はこの現象、「ジャネーの法則」と呼ばれています。 ジャネーの法則とは? フランスの哲学者ポール・ジャネが提唱したこの法則は、年齢を重ねるごとに時間の経過が速く感じられるというものです。 例えば…🔹 50歳の人にとっての1年は、人生の50分の […]