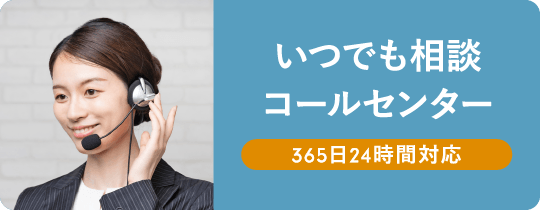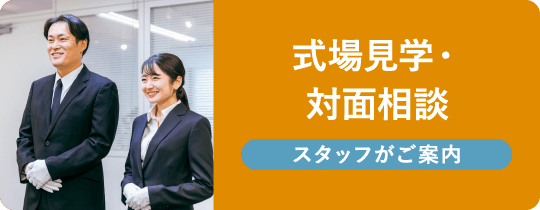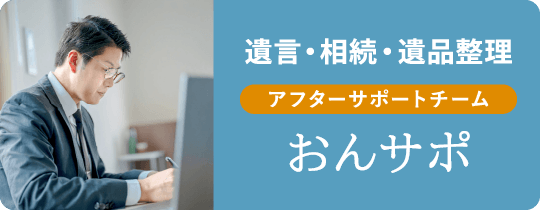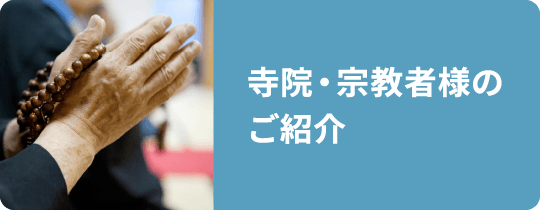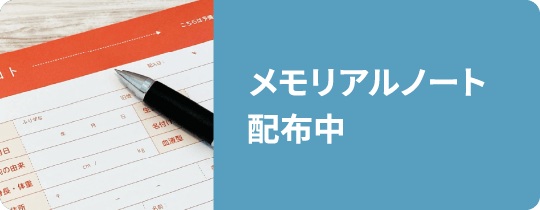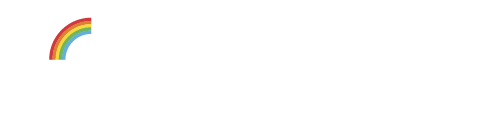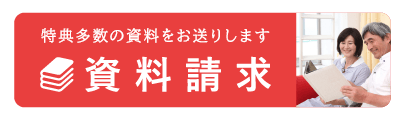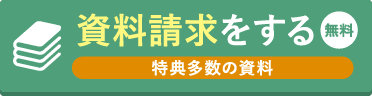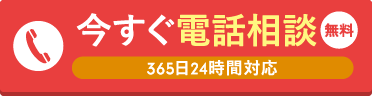お盆について

お盆の本来の意味と風習
お盆と聞くと、多くの人がお盆休みを思い浮かべます。一般的には8月13日から16日がその期間とされていますが、本来の意味は、先祖の霊をお迎えして供養する行事です。お盆の期間は地域や宗派、旧暦と新暦の違いによって異なり、たとえば東京近郊では7月13日~16日に行われることもあります。しかし、全国的には8月13日~16日の4日間をお盆として過ごす地域が最も多いとされています。
お盆の主な風習
お盆には、地域や宗派によって様々な風習がありますが、基本的な流れとしては以下のようになります:
- 13日に迎え火を焚いて先祖の霊をお迎えします。
- お墓参りをし、故人を偲びます。
- ナスやキュウリに割り箸を刺して作る牛や馬、水の子(刻んだナスやキュウリ、洗った米をハスの葉やサトイモの葉に盛り付けた供物)を飾ります。
- 16日には送り火を焚き、再び霊をあの世へ送り出します。
これらの行為はすべて、先祖の霊を供養し感謝の気持ちを伝えることを目的としています。
新盆(初盆)の特別な意味
家族が初めて亡くなられた場合、四十九日の忌明け後、初めて迎えるお盆を新盆(初盆)と言います。もし四十九日以内にお盆が訪れる場合は、その翌年が新盆となります。新盆では、特別に白提灯を玄関や部屋、仏壇の前に飾る風習があります。この白提灯は、故人が迷わず家に帰れるようにとの思いを込めて飾られるものです。
お盆の大切さ
お盆は、家族が一堂に会し、先祖の霊を供養することで絆を深める重要な機会です。特に新盆を迎えるご家庭では、白提灯や供物を用意し、丁寧に霊を迎え入れ送り出すことで、心穏やかな供養の時間を過ごすことができるでしょう。